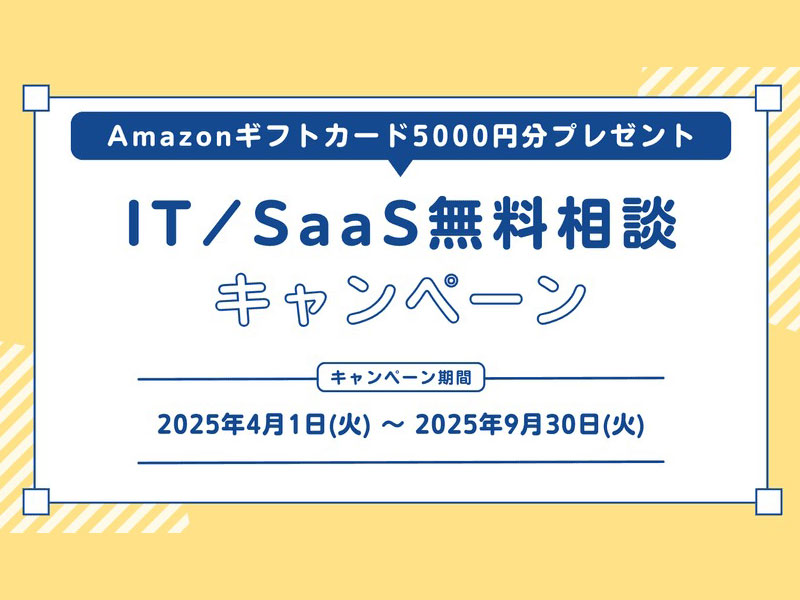- ITmedia ビジネスオンライン
- 勃発・EV戦国時代 勝つのは「提携」のソニー・ホンダか 「ケイレ...
勃発・EV戦国時代 勝つのは「提携」のソニー・ホンダか 「ケイレツ+買収」のトヨタか 「水平分業」のアップルか:意外と難しい「業務提携」だが……(1/3 ページ)
「なるほど、その組手か!」と、電機自動車(EV)およびモビリティ分野でのホンダとソニーの業務提携発表を聞いて、思わず膝をたたきました。
以前、拙稿ではソニーがEV事業進出を正式発表したタイミングでEV事業を取り巻く状況について取り上げました。その中で、それぞれに長所・短所がある既存自動車メーカー、新興のEV専業メーカー、新参のIT大手各社の優勝劣敗は、その協業の行方がポイントになるのではないかと書きました。それだけに、既存大手自動車メーカーのホンダとIT大手で台風の目的存在であるソニーの提携発表は、大きな衝撃をもって受け止めました。
【参考】ソニーも参入を発表した群雄割拠のEV市場 勝つのは古豪か、新参者か、よそ者か
ソニーがEV業界参入を表明した折に、そのEV製造の行方を想像して真っ先に思いを巡らせたのは、自動車業界国内最大手であるトヨタとの提携でした。しかし、どうにもしっくりきません。そのとき、理由までは十分に考えなかったのですが、直感的に実現性が薄い気がしたのです。ならば日産か――。とはいえフランス政府資本の入ったルノーを含む3社提携の複雑な状況から、さらに可能性が低いように思われました。むしろ現実的な可能性は、米国にも強い足場を持つソニーの企業文化を鑑みて、米国のメーカーとの提携かもしれないと思った次第です。
その時点でホンダを度外視していたのは、同社が2040年までの全新車EV化を表明しながらも、同時に中国市場でのEVシェア獲得に意欲を見せていたことにあります。安価なEVが急速に勢力を伸ばしている中国の状況から考え、ソニーとは目指すものが違うと捉えていたのです。従って、ソニーの業界参入表明から2カ月で、両社が業務提携に至った流れは衝撃的でした。当然、以前から水面下での交渉が進められてはいたのだろうとは思いましたが、会見で21年夏以降わずか半年の提携交渉であったと聞き、驚きと同時に双方の企業文化を考えれば「ウマが合う」かもと合点もいき、膝をたたいたわけなのです。
というのは、基本的に両社は非オーナー系経営であるということがあります。しかも、ともに井深大、本田宗一郎という存在感にあふれる技術系創業者がおり、その創業者によって築かれた技術開発におけるチャレンジ精神が企業文化として根付いている、という大きな共通項があるからです。両社ともに利益度外視で将来を見据えたロボット開発に力を入れ、ASIMO、aiboを世に送り出した文化はその象徴ともいえます。企業文化はトップ人事以上に企業を左右する重要な要素であり、経営統合、合併はもとより業務提携においても、それがうまくいくかいかないかの8割以上はこの点に懸かっている、といってもいいでしょう。
経営統合・合併より「提携」が難しい
提携が経営統合や合併よりもさらに難しいのは、ほとんどの場合、企業文化の違いから主導権争いが発生し、共同事業を進める中で意見対立が激しくなって、うまくいかなくなることが多いためです。合併においても、力関係が明確な吸収統合や吸収合併はうまくいくものの、対等合併はうまくいかないというケースが多いことからもその点は明白です。
10年ほど前の話ですが、飲料メーカー大手のキリンとサントリーが経営統合を表明しながらも結局実現しなかった、という出来事もありました。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング

 なぜ、ソニーとホンダが提携するのか スピード合意の裏に“EVの地殻変動”
なぜ、ソニーとホンダが提携するのか スピード合意の裏に“EVの地殻変動” ソニーも参入 各社からEV出そろう2022年、消費者は本当にEVを選ぶ?
ソニーも参入 各社からEV出そろう2022年、消費者は本当にEVを選ぶ? ソニーも参入を発表した群雄割拠のEV市場 勝つのは古豪か、新参者か、よそ者か
ソニーも参入を発表した群雄割拠のEV市場 勝つのは古豪か、新参者か、よそ者か 日本から百貨店がなくなる日――そごう・西武の売却から考える“オワコン業界”の今後
日本から百貨店がなくなる日――そごう・西武の売却から考える“オワコン業界”の今後 「名門銀行子孫」のあっけない幕切れ 新生銀行・SBI・金融庁、TOB騒動の背景に三者三様の失策
「名門銀行子孫」のあっけない幕切れ 新生銀行・SBI・金融庁、TOB騒動の背景に三者三様の失策