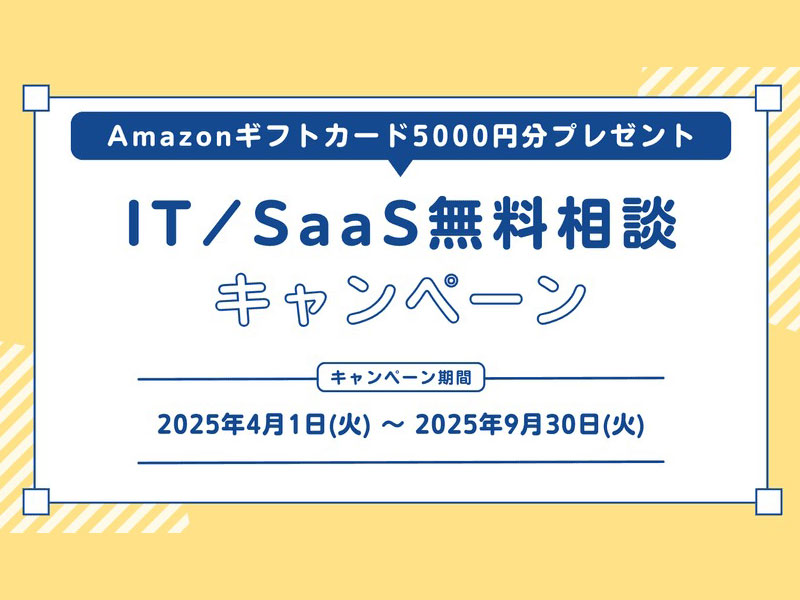- ITmedia ビジネスオンライン
- マツダの第6世代延命計画は成るか?:池田直渡「週刊モータージャ...
マツダの第6世代延命計画は成るか?:池田直渡「週刊モータージャーナル」(1/7 ページ)
» 2021年01月25日 07時00分 公開
[池田直渡,ITmedia]
CX-5はマツダにとって重要なクルマ。稼ぎ頭であり屋台骨だ。そのCX-5が年次改良を受けた。
というクルマの個別の話に入る前に、今のマツダの状況を整理しておかなくてはならない。というか申し訳ないが、話のほとんどはそれに終始する。
コモンアーキテクチャー
マツダはSKYACTIV技術を全面的に投入したモデルを第6世代と位置づけ、2012年にデビューした初代CX-5から展開をスタートさせた。これは別の角度から見れば「コモンアーキテクチャー戦略」でもある。
マツダはラインアップの全モデルの着地点をあらかじめ想定し、それらに共通の基礎技術をSKYACTIVとして開発する。コンピュータでいうならば、これがOSだ。その上にブロックを積み上げるような形で、個別のモデルの要素を加えて個性的な車種を開発していく。これがアプリケーションに当たる。
OSが進化すれば、アプリでできることも一緒に進化する。ラインアップ全モデルを一斉にアップグレードすることができる。それによって何を狙っているのかといえば、効率よく優れた製品を生み出し続け、それを進化させ続けることである。
旧来のやり方であれば、ベース車両を1台作って、それを変奏曲のようにアレンジすることで数車種の派生モデルを作る。それでラインアップ全体を作るにはベース車両を複数作らねばならないので、開発コストがかかるし、そうやってできたクルマのアレンジで変えられる範囲は限られてくるから、派生車種同士に差異が少なくなる。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング
アイティメディアからのお知らせ
SpecialPR

 藤原副社長、ラージプラットフォーム投入が遅れる理由を教えてください
藤原副社長、ラージプラットフォーム投入が遅れる理由を教えてください ラージの遅れは「7世代の技術を現行世代に入れる。もうそれをするしかない」 藤原副社長インタビュー(3)
ラージの遅れは「7世代の技術を現行世代に入れる。もうそれをするしかない」 藤原副社長インタビュー(3) MX-30にだまされるな
MX-30にだまされるな マツダMX-30で1800キロ走って見えたもの
マツダMX-30で1800キロ走って見えたもの CX-5に気筒休止エンジン登場
CX-5に気筒休止エンジン登場