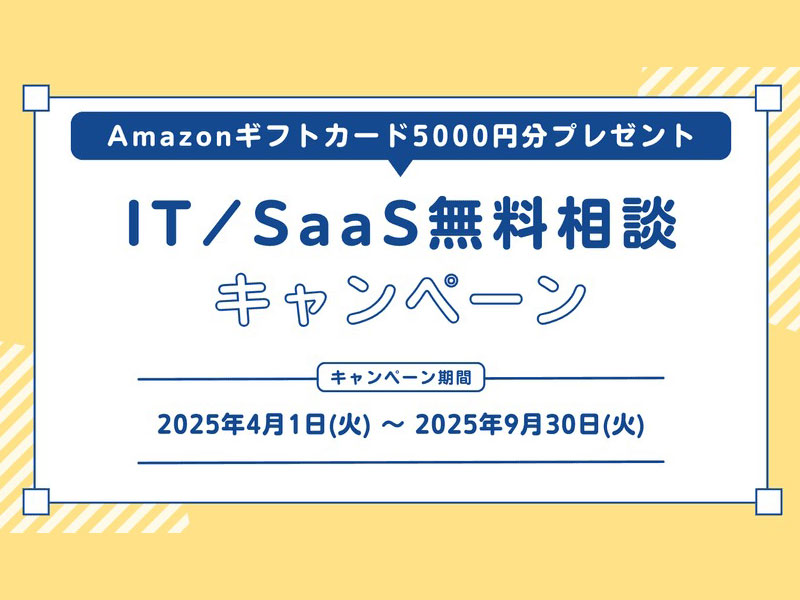- ITmedia ビジネスオンライン
- 藤原副社長、ラージプラットフォーム投入が遅れる理由を教えてくだ...
藤原副社長、ラージプラットフォーム投入が遅れる理由を教えてください:池田直渡「週刊モータージャーナル」(1/5 ページ)
マツダの藤原清志副社長のインタビューに基づいた解説記事の第2弾は、ラージプラットフォームの話である(第一弾、「藤原副社長、マツダが売れなくなったって本当ですか?」はこちら)。
北米マーケットを見据えた戦略
現在マツダは第7世代商品群をスタートさせたばかり。すでにMAZDA3とCX-30がデビューしている。これはスモールプラットフォームと呼ばれるFF用シャシーであり、MAZDA2(旧デミオ)とMAZDA3を中核としたBセグメント、Cセグメント用のプラットフォームである。
この上に位置するCX-5とCX-8、中国向けのCX-4、北米向けのCX-9、そしてMAZDA6については、すべてラージプラットフォームと呼ばれる別のシャシーをデビューさせる予定だ。マツダは第6世代をスタートさせる時、コモンアーキテクチャー構想によって、全てのクルマを同じ考え方で設計し、同じラインで混流生産することを目指した。その改革を成功させることで、破綻寸前の経営から脱却した。
しかし、その成功によって、生産・販売台数が伸張した結果、全ての製品を同じラインで混流生産する意味が薄れ始めた。200万台に向けて考えれば、もう少しシャシーの役割を個別に変えたい。特に今マツダが力を入れている北米での商品力を考えると、FF+4気筒をベースに置いていたのでは、商品性が足りない。
日本人には想像し難いが、北米では4気筒は安物というイメージが強い。V8が好まれるお国柄を考慮すれば、多気筒化しないと、ハンデを負った状態で戦わなくてはならなくなる。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
続きを読むには、コメントの利用規約に同意し「アイティメディアID」および「ITmedia ビジネスオンライン通信」の登録が必要です
Special
PR注目記事ランキング

 藤原副社長、マツダが売れなくなったって本当ですか?
藤原副社長、マツダが売れなくなったって本当ですか? 自動車を売るビジネスの本質 マツダの戦略
自動車を売るビジネスの本質 マツダの戦略 マツダCX-30の発売と、SKYACTIV-X延期の真相
マツダCX-30の発売と、SKYACTIV-X延期の真相 EVにマツダが後発で打って出る勝算
EVにマツダが後発で打って出る勝算 マツダのEVは何が新しいのか?(前編)
マツダのEVは何が新しいのか?(前編)