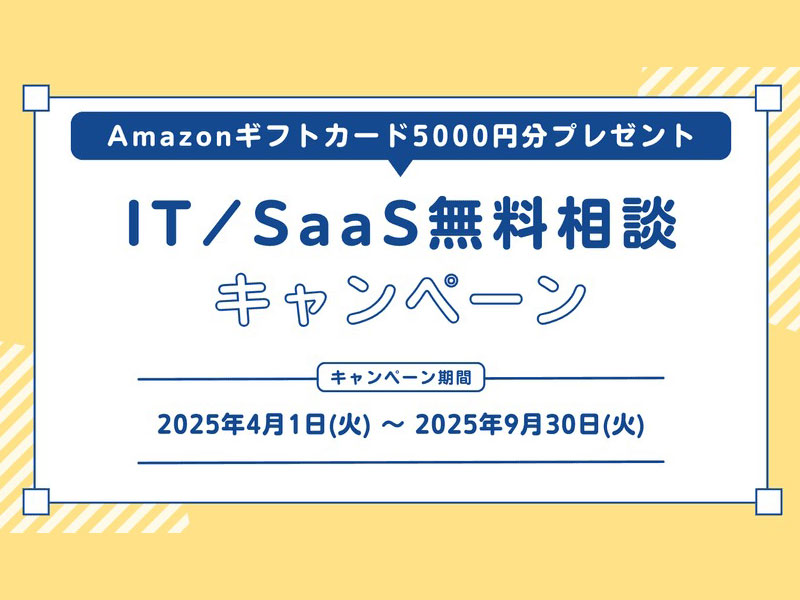- ITmedia ビジネスオンライン
- #SHIFT
- 「がん離職」を防ぐために100万円支給――「社員の病気=経営課題...
「がん離職」を防ぐために100万円支給――「社員の病気=経営課題」に会社はどう向き合ったか:連載「病と仕事」
国立がん研究センターによると、2017年にがんにより死亡した人は37万3334人に上る。高齢になるほど、がんの罹患率は高まるが、働き盛りの年齢でがんを発症する可能性もゼロではない。精神面、経済面、仕事面のケアが求められる従業員の病に対して、職場はどういったサポートができるのだろうか。
がんに罹患した社員に対する基金を創設したガデリウスグループ(東京都港区)の経営統括本部本部長の池田佳久さんに創設の経緯などを取材し、がん基金を利用した当事者にも話を聞いた。
 池田佳久(いけだ・よしひさ)1996年にガデリウス・トレーディング株式会社(現・ガデリウス・インダストリー株式会社)に入社。印刷器材事業部、LEH建材事業部事業部長を経て2010年よりガデリウス・インダストリー株式会社 取締役。現在はガデリウス・メディカル株式会社、ガデリウス・サービス・エンジニアリング株式会社の取締役も兼務する。2015年1月よりガデリウス・ホールディング株式会社経営統括本部長
池田佳久(いけだ・よしひさ)1996年にガデリウス・トレーディング株式会社(現・ガデリウス・インダストリー株式会社)に入社。印刷器材事業部、LEH建材事業部事業部長を経て2010年よりガデリウス・インダストリー株式会社 取締役。現在はガデリウス・メディカル株式会社、ガデリウス・サービス・エンジニアリング株式会社の取締役も兼務する。2015年1月よりガデリウス・ホールディング株式会社経営統括本部長社員の生活が、がんの治療費で立ち行かなくなる
ガデリウスグループ(ガデリウス・ホールディング株式会社、ガデリウス・インダストリー株式会社、ガデリウス・メディカル株式会社)は、1890年にスウェーデンで創業した貿易商社だ。1907年に創業者であるクヌート・ガデリウス氏が横浜に日本初の支店を開設し、現在は専門商社として、建設機械、生産機械や産業機材、印刷器材、建築材料、医療機械・医療器具などの輸入販売を手掛けている。
同社にはグループ全体で約180人の従業員(パートを除く)が在籍し、主な年齢層は40代と50代に集中している。同社において、2017年に新たに創立された福利厚生制度が、「ガデリウスがん基金」(以下「がん基金」)だ。この制度は、がんに罹患した社員に対して、会社から治療費として一律で100万円を支給し、がんの治療費に充ててもらうことを目的としている。制度が設立された経緯について池田さんはこのように話す。
「16年から17年にかけて、当社の社員が立て続けにがんで亡くなりました。このうち1人は治療期間が長期となり、抗がん剤の治療費などで多額の費用がかかっていたようです。がんの治療内容によっては社員の生活が立ち行かなくなることを知った社長のヨスタ・ティレフォーシュの発案により、がん基金が設立されました」
同社では、毎年11月から12月にかけて、「サンタツアー」と称する行事が開かれている。サンタツアーは、社長が全国の事務所を巡り、クリスマスギフトを渡し懇親会で社員をねぎらうことを目的として行われているものだが、17年のサンタツアーでは、がん基金の趣旨について社長から社員へ直接説明がなされたという。
「がん基金について、社員からは『ぜひやってほしい』といった賛同の声が多く寄せられました。サンタツアーは、社員のねぎらいを目的とする一方で、社長にとっては社員の声を直接聞く場でもあります。サンタツアーをきっかけにして生まれる福利厚生制度も多く、男性の育児休業休暇2週間の義務化、消費税増税時の手当金補助、屋根付き駐輪場の設置といった制度がこれまでに生まれています」(池田佳久さん)
健康な人にも突然もたらされる、がんの宣告
同社には、がん基金以外にも、がんに罹患した社員が活用できる制度がある。例えば、未使用の有給休暇を1年につき最大10日間、療養特別休暇として最大75日間積み立てられる制度。そして、未使用の有給休暇を他の社員に寄付できるという制度も設けてある。
現役の会社員にとって、がんに罹患した際の経済的損失は治療費にとどまらない。有給休暇を使い切った場合、一定期間は傷病手当金による補助はあるものの、収入減は割けられないからだ。ガデリウスグループの福利厚生制度は、こうした問題に対する支援になるだろう。
1月に制定された「年次有給休暇の寄付」制度は、10月31日まで募集を呼び掛け、28人の社員から(1人当たり1日から15日)合計224日の寄付の申し出があったという。寄付された有給休暇を使用することで、該当社員は会社を辞めることなく治療を続けることがしやすくなる。
このほか、テレワークや時短勤務、コアタイムなしのフレックス勤務制度といった柔軟な働き方を可能とする仕組みや、相談窓口の設置といった支援制度を用意している同社は、18年に、がんの治療をしながら働きやすい職場や社会を実現するために各企業の取り組みを表彰する「がんアライアワード」において、ゴールド賞を受賞した。
このように、日本企業ではあまり見られないユニークな福利厚生制度を多数導入している同社だが、これらの取り組みについて、社員にはどのように受け止められているのだろうか。乳がんに罹患し、がん基金などの制度を利用したという高原由紀子さん(正確には高は「はしごだか」)にも話を聞いた。高原さんは、がんを認識するまでの経緯をこのように振り返る。
「最初に違和感に気づいたのは、18年2月のことです。胸のあたりがかゆくなり、掻いてみると引っ掛かりを感じました。それが異様に硬くて心配になり、3月に病院で受診すると、「おそらく大丈夫でしょう」と言われたのですが、その後、再検査を受けると“しこり”が大きくなっていて、さらに細胞診、組織診を経て、8月に乳がん暫定ステージ1という診断結果が出ました。
細胞診の結果、『良くないものが出ました』と初めて宣告されたときには、診断を受け入れませんでした。それまで、大きな病気をしたこともなかったので……『まさか自分が』と……。『検査ミスに違いない』と信じることにしたんです」
その後、組織診で悪性度が比較的低いがんであることや、暫定ステージが1だということが分かった。その説明に納得ができたので、医師を信頼して転院はせずに、手術を受けることを決意したと話す。『良くない』と分かった段階で手術室はおさえられており、診断結果が出た8月のうちに手術を受けることができたという。
「組織診の検査承諾のとき、サインをする手が震えていたことは、今でも覚えています。『いつまで生きられるのだろう』と、不安で押しつぶされそうでした。ただ、会社のがん基金を利用して元気に復帰された方がいらっしゃることを知っていたので、少なくとも経済面の不安を感じたことはなかったと思います」
高原さんは、手術から2日後に退院の日を迎えることができた。しかし、手術で切除した部分の病理検査はその後も引き続きおこなわれ、病巣が完全に取りきれたかどうか、リンパへの転移がないかどうかが精密に調べられる。最終的な診断と治療方法は、その結果を待たなければ決まらない。そして手術から1カ月後に最終的にステージ1が確定し、ほぼ当初の診断通りに、20日の放射線治療と、10年のホルモン剤療法がとられることになった。
「がん離職」は会社の「経営課題」
放射線治療は1カ月、土日祝を除いて毎日継続しなければならなかったため、午前中は休暇を取り、午後から出社していたという。がんの治療にかかる時間や費用はさまざまであり、予測することが難しい。高原さんの場合はどうだったのか。
「高額療養費制度を利用したので、手術などにかかる基本的な費用は毎月決まっている限度額ですみました。ただ、この他に入院中の差額ベッド代や、退院後の放射線治療などの費用もかかりましたから、私の場合はトータルで50万円ほど必要になったと記憶しています。今後服用するお薬に30~40万円かかることを考えあわせても、全てがん基金で賄えます。また、入院と通院のために休暇が必要となりましたが、療養休暇を利用して、経済的な心配をする必要もなく助かりました」
ガデリウスグループが行っているがん基金などの支援制度は、経済的な側面からがんの治療をサポートするものである。しかし、池田さんは経済的側面よりも、むしろ精神的側面において、職場による支援が求められると話す。
「介護離職の問題と同様に、“がん離職”も会社として取り組むべき大きな問題だと考えています。がんにかかると、多くの場合、社員はまず『会社に言えない』という問題を抱え、やがて、「会社を辞めなければならない」と思い悩んでしまうようです。当社の場合、がん基金などの支援制度を用意し、会社としてがんの社員をサポートする姿勢を打ち出しているので、これが気持ちの安心感につながっているのではないでしょうか」
ガデリウスグループには、5つの理念があり、その3つ目の理念には、「従業員一人ひとりの心身の健康を第一に考え、働きやすい職場環境を提供します」との文言が含まれている。このような意識は、労働人口が減りゆく日本においては、今後ますます重要になるのではないだろうか。高原さんは、最後にこのように締めくくった。
「会社に支援制度があると、周りのがんの人を支えようという意識が生まれやすくなるということがあるのではないでしょうか。私は、がんのことを明かした同僚から、『自分にできることがあれば、何でもやりますから、治療を最優先にしてください』と声をかけてもらい、人の温かみを身に染みて感じました。私も、これから社内に病気の問題を抱える人がいたら、自分がしてもらったのと同じように、支えになって差し上げたいと思います」
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング




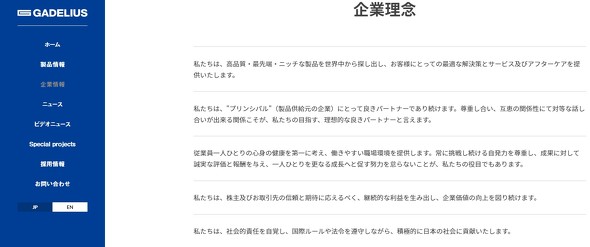

 25歳で「がん宣告」を受けた営業マンが「働くこと」を諦めなかった理由――企業は病にどう寄り添えるのか
25歳で「がん宣告」を受けた営業マンが「働くこと」を諦めなかった理由――企業は病にどう寄り添えるのか ホリエモンが政治家に頭を下げてまで「子宮頸がんワクチン」を推進する理由
ホリエモンが政治家に頭を下げてまで「子宮頸がんワクチン」を推進する理由 余命1年を宣告され単身渡米 がんを乗り越え「2度の世界女王」に輝いたバックギャモン選手
余命1年を宣告され単身渡米 がんを乗り越え「2度の世界女王」に輝いたバックギャモン選手 ホリエモンが「ピロリ菌検査」と「HPVワクチン」を推進し続ける真意
ホリエモンが「ピロリ菌検査」と「HPVワクチン」を推進し続ける真意 ホリエモンが糖尿病の「不都合な真実」をホラー映画で訴える理由
ホリエモンが糖尿病の「不都合な真実」をホラー映画で訴える理由 ホリエモンが課題だらけの医療業界を斬る! 「大学の医学部で経営も教えるべき」
ホリエモンが課題だらけの医療業界を斬る! 「大学の医学部で経営も教えるべき」